こんにちは徳島整体院 内海です。
近年、めまいに悩む人が増えているようなので、今回はめまいについて記事にしようと思います
めまいとは

めまいとは自分や周囲のものはうごいていないのに、動いているように感じる異常な感覚を指します。
めまいは主にどんな症状か!?
天井がぐるぐる回る。頭がくらくらする。スポンジの上を歩いているようにフワフワする。目の前の景色がゆれる。などです。
めまいの大きな分類
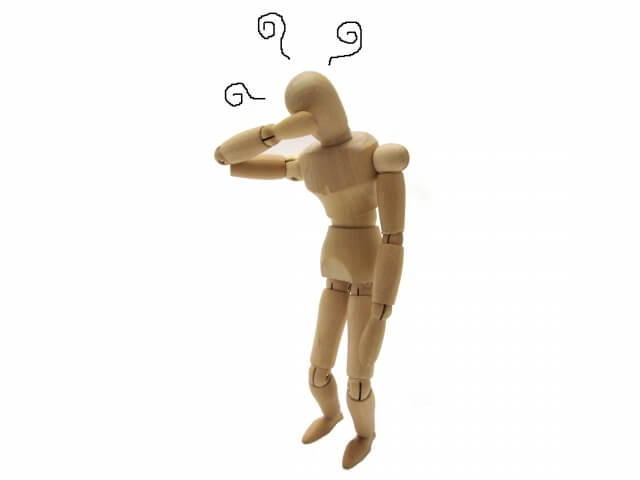
めまいの種類を大きく分けると、回転性のめまいと浮動性のめまいに大別されます。
どちらも吐き気や嘔吐を伴うことがあります。
回転性めまいの特徴

自分がぐるぐる回るように感じるめまいです。縦回転(垂直回転)してように感じるタイプもありますが、大半は横回転(水平回転)と感じる人が多いといわれます。身体が横に引っ張られるように感じる人も中にはいます。
回転性のめまいは一定期間でその後は消えるのが一般的です。
浮動性めまいの特徴
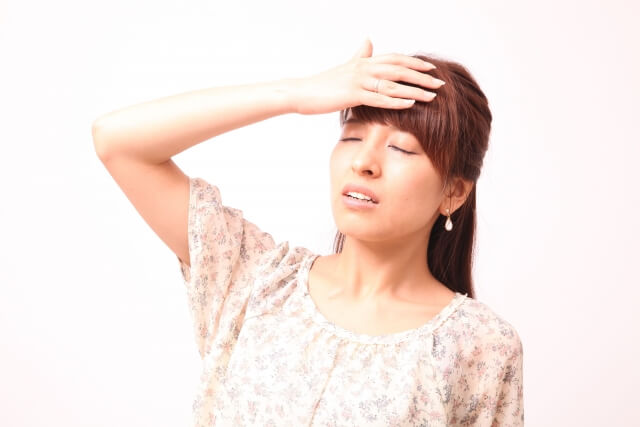
ふわふわと浮いているように感じるめまいです。
回転性のめまいのように一定期間で消える場合もありますが、何カ月や何年も続く浮動性のめまいは高齢の方によくみられるようです。
めまいの種類別の主な原因
回転性のめまいは耳の病気で起こることが多く、浮動性のめまいは脳血管障害、低血圧や貧血などの全身症状、脳の病気、心因的なもの、薬剤の副作用などによって起こることが一般的です。
回転性のめまいの主な原因
メニエール病
めまいの中でも知名度が高いのが「メニエール病」です。
メニエール病は。難聴や耳鳴り、耳閉感(耳が詰まった感じ)など、聴覚症状を伴うのが特徴です。
めまいの発作を繰り返すうちに、聴力が低下していくケースも少なくありません。
詳しくはこちらへ⇒メニエール病について
耳管開放症と耳管狭窄症
耳管開放症
「耳管開放症」によってめまいが起こることがあります。
耳管の役目は中耳の鼓室と外気の気圧に差が生じたとき、気圧調整をすることです。
通常は、耳管は閉じていることで、鼓膜の振動が安定し、人声や物音が効きやすい状態に保たれています。また、上咽頭には雑菌が多いのですが、耳管が閉じていることで中耳内への雑菌の侵入を防ぎ、感染が起こらないようになっています。
この耳管が開きっ放しになることを耳管開放症と呼びます。
耳管狭窄症
耳管開放症に似た症状をもたらすものに「耳管狭窄症」があります。これはカビやアレルギー性鼻炎などで耳管の粘膜に炎症が発生し、耳管が腫れて塞がるために起こります。以前はこの病気の方が多かったようです。
詳しくは⇒耳管開放症と耳管狭窄症について詳細
良性発作性頭位めまい
耳が原因で起こるめまいの中で最も多いのは「良性発作性頭位めまい」です。「良性」とはめまい以外の症状がないこと、「発作性」とはめまいが起こるのは時々で、30秒くらいで治まる、比較的軽い症状との意味合いでしょう。
このめまい症では、寝返りを打ったとき、寝た姿勢から起き上がったとき、靴ひもを結ぶとき、洗濯物を干すときなど、頭を特定の方向に動かしたときに回転性めまいが起こる。男女比は、女性が男性の4~5倍も多いようです。年齢は50~60代以降に多く起こります。
詳しくはこちら⇒良性発作性めまいについて
浮動性のめまいの原因
全身症状や心因性によるもの
脳梗塞や脳出血などの脳の循環障害
首コリや肩こり
低血圧症や低酸素血症、貧血、低血糖、特定のホルモン変化(甲状腺の病気、月経、妊娠など)
脳腫瘍やてんかん。
パニック障害、過換気症候群、不安、抑うつ。
高齢者においては、加齢に伴う視覚や前庭感覚などの機能低下によって二次的に生じる場合もあります。
薬剤の作用
薬によっては副作用として浮動性のめまいが生じることがあるほか、高血圧の方では降圧剤を多く服用してしまうことで、血圧が異常に低くなり起こることもあります。
めまいを軽くみない
めまいにはまれに脳卒中などの脳の病気で起こることもあ
りますので軽く考えてはいけません。片側の手足の動きが
よくない。半身の感覚がおかしい。ろれつが回らない、物
が二重に見える、意識がもうろうとするなどの症状を伴う
場合は病院を受診することが必要です。






